機械故障の原因究明に欠かせない故障解析手法と基本手順!専門家に依頼するメリットも解説
製造現場での機械故障は、生産停止や品質低下、さらには安全リスクを引き起こすため、迅速かつ的確な原因究明が求められます。故障解析には多様な手法があり、それぞれの特性を理解し適切に活用することが、トラブルの早期解決と再発防止につながります。
こちらでは、故障解析における主要な原因究明手法や、具体的な手順、専門家に依頼するメリットをご紹介します。
故障解析における主要な原因究明手法
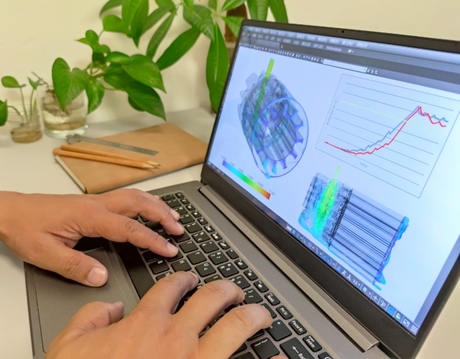
機械の故障は、製造ラインの停止や製品の品質低下、さらには安全面でのリスクにもつながる重大な問題です。そのため、故障発生時には速やかに原因を究明し、再発を防ぐ対策を講じることが欠かせません。故障解析には多くの手法が存在しますが、その中でも代表的で効果的な方法をご紹介します。
故障モード影響解析(FMEA)
FMEAは、設計段階や運用開始後のメンテナンス計画立案などに幅広く用いられる解析手法です。機械の各コンポーネントや機能に対して、どのような故障モード(壊れ方)が想定されるかを洗い出し、それらが引き起こす影響を評価します。故障の発生頻度や影響度、検出可能性の3つの要素を組み合わせた「リスク優先数(RPN)」を算出し、リスクの高い箇所を優先的に対策することで効率的な予防保全を実現します。
この手法は、単に故障した部品を修理するだけでなく、設計や工程の改善につなげるための非常に有効なアプローチです。例えば、ある軸受けに繰り返し過負荷がかかって摩耗しやすい場合、材料の変更や負荷の分散を設計に取り入れることが可能です。
物理的・非破壊検査技術
故障現場の検査においては、目視だけでは見つけられない異常を発見することが重要です。ここで非破壊検査技術が活躍します。代表的な技術には以下があります。
- 外観検査(目視)
- 実体顕微鏡観察
- 表面粗さ測定
- 表面元素分析
- X線CTスキャン
- 潤滑剤化学分析
これらの手法を組み合わせることで、故障発生のメカニズムをより正確に把握し、適切な修復方法を決定できます。加えて、故障前の異常検知に活用し、計画的な保全も可能となります。
根本原因分析(Root Cause Analysis:RCA)
故障の表面的な原因だけを修理しても、根本的な問題が解決されなければ再発は避けられません。RCAは、「なぜ」を何度も繰り返して本質的な原因にたどり着く分析手法です。例えば、ベアリングの摩耗という故障が起きた場合、「なぜ摩耗したのか?」を問うことで「潤滑不良」「過負荷」「異物混入」など複数の原因が想定されます。さらに「なぜ潤滑不良が発生したのか?」まで掘り下げることで、保守管理の手順不足や作業者の教育不足といった根本的な問題が明らかになることもあります。
このように問題の原因を多角的に掘り下げることは、再発防止に欠かせない工程です。RCAの手法には、「5Why分析」「魚骨図(フィッシュボーンダイアグラム)」などがあり、現場での議論や記録作成にも活用されています。
故障解析の基本的な手順

故障解析をスムーズに進めるには、一連の流れを体系的に踏むことが重要です。以下に基本的な手順を詳しく説明します。
1.故障現象の把握と詳細記録
故障が発生した際、最初に行うべきは現象の正確な把握です。故障の具体的な状況や異常の兆候、時間帯や環境条件などを漏れなく記録します。これには作業者からの聞き取りや、センサー・監視装置のログも活用されます。
ただ「動かない」というだけでなく、「何時頃から動作異常が発生したか」「どの部分に異音や異臭があるか」などの詳細情報が、後の原因分析に大きく役立ちます。
2.現場での検査と計測
次に、故障箇所の外観検査や必要に応じて機械の分解調査を行います。部品の摩耗や変形、破損、錆・腐食の有無などを確認し、異常の特徴を観察します。振動測定器や赤外線カメラなどの計測器を用いて、目に見えない異常を検出することも重要です。
この段階で故障が特定の部品に限られるのか、あるいはシステム全体の問題なのかを判断し、解析の方向性を決定します。
3.データ分析と原因の絞り込み
集めた情報や検査結果をもとに、原因を詳細に検討します。設計ミスや製造不良、運用ミス、材料の劣化、環境要因など複数の可能性を比較検討します。前述のFMEAやRCAの手法を用いて、故障の発生メカニズムを科学的に分析し、真の原因に迫ります。
この段階では多職種の技術者が連携して知見を持ち寄ることが多く、より精度の高い原因究明が期待できます。
4.再発防止策の立案と実施
原因が判明したら、修理だけにとどまらず、根本的な改善策を策定します。設計の改良、作業手順の見直し、保守点検計画の強化など、多面的に対策を講じます。これにより、同じ故障が繰り返されるリスクを大幅に減らせます。
また、改善策の実行後は、効果の検証期間を設けることが重要です。一定期間モニタリングし、問題が再発していないかを確認します。
5.継続的なモニタリングとフィードバック
故障解析は一度で終わるものではありません。改善策を実施した後も、継続的に機械の状態を監視し、新たな問題を早期に察知できる体制を整える必要があります。さらに得られた知見は社内のナレッジとして蓄積し、将来の設計や運用に活かすことで、品質向上とコスト削減を両立させます。
故障解析の専門家に依頼するメリット
社内に解析技術者がいても、特に複雑な故障や原因不明のトラブルに対しては専門家の力が不可欠です。故障解析の専門家に依頼することで、次のような大きなメリットが得られます。
高度な知見と豊富な経験
故障解析の専門家は、業界内外の多種多様な故障事例に精通しています。経験にもとづく直感やパターン認識力により、問題の本質を素早く捉え、精度の高い解析が可能です。これにより解析期間の短縮と早期の復旧が実現します。
再発防止につながる技術的提案
専門家による解析結果は単なる報告書では終わりません。破損原因に対する具体的な改善案、例えば潤滑条件の見直し、材質変更、機構の再設計といった提案が含まれます。これにより、同様のトラブルの再発を防ぐだけでなく、機械全体の信頼性向上にも寄与します。
外部視点による客観性
企業内での故障調査は、ともすれば先入観や既存の常識に引っ張られることがあります。外部の専門家は第三者の視点から状況を見極めるため、客観的で偏りのない判断を下すことができます。この中立性が、重大事故の未然防止や品質保証の観点から極めて重要です。
機械の故障解析を依頼するならTAS研究所へ
機械故障の原因究明を専門家に依頼したいとお考えなら、TAS研究所にお任せください。顧客の3つのT(トラブル、トライボロジー、テスティング)に対する総合的なアドバイスとソリューションを提供いたします。
機械トラブルの解決に関して、最後までしっかりとサポートいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
【トライボロジー】機械故障・解析や摩擦試験に関するコラム
- 機械故障について専門家に相談を!漏油・過熱トラブルの原因と対策
- 急ぎ対応が求められる機械故障時の注意点と早期対応のポイント
- 【機械故障】再発防止ならコンサルへ相談!メリット・選び方・具体的な進め方
- 機械故障コンサルティング完全ガイド!専門家の役割・選ぶ基準・費用について
- 【トライボロジー】自動車の摩耗の基本や試験について
- トライボロジーで探るかじりの原因と潤滑技術による防止策
- 摩擦試験の委託費用は?受託している業者の選び方や準備のポイント
- 摩擦試験における係数測定・分析の重要性と腐食がもたらす影響
- 【機械の故障解析】原因究明の手法・手順・専門家に依頼するメリットを解説
- 【機械の故障解析】焼付きの対策と疲労破壊の現象解析手法
故障解析・原因究明のご相談ならTAS研究所
| 会社名 | TAS研究所 |
|---|---|
| 電話 | 090 8324 6136 |
| suzuki@taslab.jp | |
| 受付時間 | 9:00-18:00[ 土・日・祝日除く ] |
| URL | https://taslab.jp |