【トライボロジー】自動車における摩耗のメカニズムや分類は?摩耗試験についても解説
自動車が安全かつ快適に走行するためには、エンジンやトランスミッションといった内部部品がスムーズに、そして長く機能することが不可欠です。しかし、これらの部品は常に互いに接触しながら動いており、避けられない現象が「摩耗」です。摩耗は部品の寿命や性能に大きな影響を与えるため、自動車開発において極めて重要な課題として認識されています。この摩耗、摩擦、潤滑といった現象を総合的に研究する技術分野が「トライボロジー」です。
こちらでは、自動車における摩耗の発生メカニズムから、摩耗の分類、摩耗試験の目的と、代表的な試験方法をご紹介します。
自動車における摩耗の基本

自動車のエンジンやトランスミッションなど、多くの部品は互いに接触しながら動いています。この摺動(こすれ合う動き)で発生する摩擦や摩耗、そして潤滑は、トライボロジーという技術分野で研究されています。特に摩耗は、部品の寿命や性能に大きく影響するため、自動車開発において非常に重要な課題です。
自動車における摩耗の発生メカニズム
自動車内部での摩耗は、動く部品同士が接触し、繰り返しの摩擦力が加わることで発生します。特にエンジンのピストンリングとシリンダー壁の間は、極端に過酷な環境です。数百度に達する高温と高圧の中で、数千回/分という高速往復運動が繰り返されるため、潤滑油による油膜保持が困難になる瞬間があります。
この油膜が不十分な状態では、金属同士が直接接触しやすくなり、「接触アスペクト」が増加、局所的に高い応力がかかって微小な溶着・剥離が発生します。これが摩耗の進行を加速させる主な原因です。さらに燃焼ガスのスラッジや微粒子が入り込み、研磨摩耗を促進する場合もあります。
摩耗の分類とそれぞれの特徴
アブレシブ摩耗(研磨摩耗)
車両の走行中に吸い込まれるほこりや微細な異物は、エンジン内部で硬い粒子として摩擦面に入り込みます。これらが砥石のように働き、表面を削り取る摩耗です。エアフィルターの性能やエンジンの密封性が悪いと、この摩耗は顕著に現れます。
凝着摩耗
凝着摩耗は、部品同士が接触する際に、局所的な高圧と高温によって金属表面が微小に溶融し、凝着することで発生します。この凝着部分が、その後の運動で引き剥がされる際に、相手材の表面を削り取ったり、微小な破片を生成したりします。潤滑油が不足し、金属同士が直接接触しやすい条件下で起こりやすいのが特徴です。
疲労摩耗
疲労摩耗は、金属表面に繰り返し応力が加わることで発生する摩耗です。特に、ベアリングやギアなど、繰り返し荷重を受ける部品で問題となります。微小な表面の損傷が核となり、徐々に亀裂が進展し、最終的に材料の一部が剥がれ落ちます。
腐食摩耗
腐食摩耗は、化学的腐食と機械的摩耗が組み合わさって発生する現象です。腐食性環境下では、金属表面に腐食生成物が形成され、これが摩擦によって除去されることで摩耗が進行します。特に、自動車の排気系統部品や、燃料噴射装置など、高温の腐食性ガスに晒される部品で問題となります。
摩耗が自動車部品の性能に与えるインパクト
自動車のエンジンや駆動系における部品摩耗は、製品寿命やユーザー満足度に直結します。摩耗による寸法変化や表面損傷が進行すれば、振動・異音・燃費悪化といった不具合が顕在化し、リコールや市場不良にもつながります。
特に自動車メーカーや部品サプライヤーにとっては、量産時に確実な品質を再現できるかどうかが重要です。摩耗に強い材料の選定や、適切な潤滑設計、加工後の表面品質のばらつき管理は、全て製品信頼性に影響を与える要素です。
摩耗試験の目的とその重要性
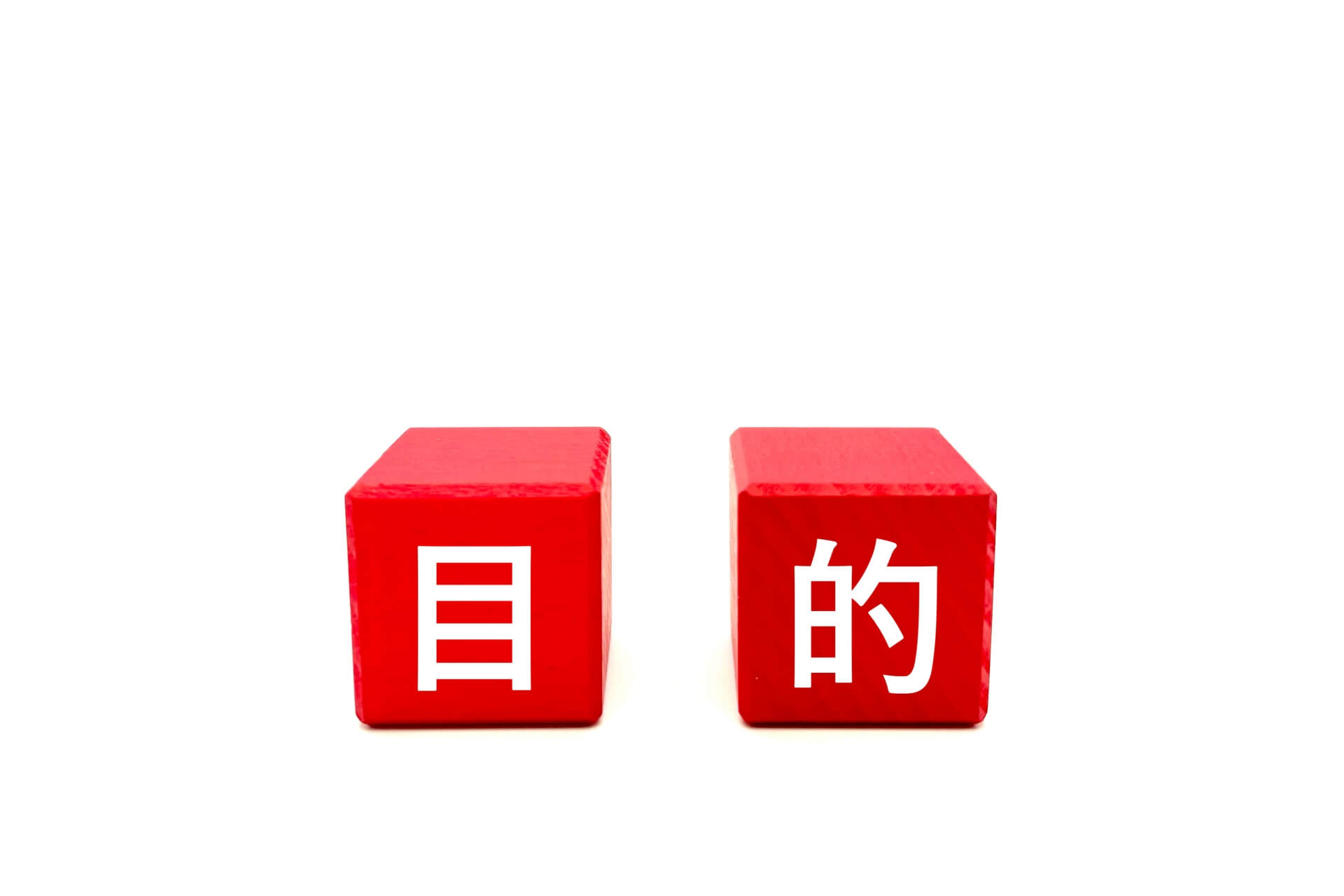
自動車部品、特にエンジン内部のような摺動部では、摩耗は避けられない現象ですが、その進行を適切に管理することが重要です。摩耗試験は、この摩耗が部品の性能や寿命にどのように影響するかを評価し、対策を講じるために不可欠です。
摩耗試験の目的とその重要性
摩耗試験は、自動車部品の耐久性を客観的に評価するための不可欠な工程です。材料選定や表面処理の効果を数値化することで、製品設計の根拠を提供します。
例えば、ある鋼材の耐摩耗性が不十分であれば、表面処理や代替材料の検討が必要です。潤滑油の評価でも、摩耗量や摩擦係数の変化は性能指標として使われ、油種の選定や添加剤の配合最適化に役立ちます。
摩耗試験によって得られた定量データは、材料選定や熱処理条件の最適化、潤滑剤の再設計といった開発活動に直接活用されます。これにより、設計初期から摩耗起因のトラブルを予防でき、試作コストやリコールリスクの低減にも貢献します。
さらに、量産段階では、摩耗評価を定期的に実施することで、設備の異常や部品供給ロット間のばらつきを早期に検出し、現場の生産安定性を高めることが可能です。つまり、摩耗試験は開発フェーズにとどまらず、全体の品質マネジメントとコスト戦略に直結する要素といえるでしょう。
代表的な試験方法の詳細解説
ボール(ピン)オンディスク試験
回転するディスク試験片の表面に、ボールまたはピンを押し付けて回転摺動させる試験です。点接触の形態を示すため大きな接触面圧を得られますが、ボールの摩耗により摩耗面積が増え、面圧が変化する可能性があります。
ボール(ピン)オンプレート試験
プレート上の試験片にボールまたはピンを押し付けた状態で、プレートを水平方向に往復摺動させる試験方法です。摩擦係数や摩耗量を計測する際に用いられます。
スラストシリンダー試験
円筒形の試験片を平板の試験片に押し付けて回転させることで、摩耗特性を評価する試験です。摩耗の進行があっても接触面積が変化しないため、主にすべり軸受けなどの焼付き荷重の評価などに適しています。
ブロックオンリング試験
リング状の試験片にブロックを押し付けて回転させる試験方法で、線接触の摩耗特性を評価する際に使用されます。摩擦開始直後は線接触ですが、摩耗の進行に伴い面接触になるため、初期と摩耗進行後で摩擦荷重が変化するのが問題です。
四球試験
三つの固定された球の上に一つの回転球を押し付けて、回転させることで摩耗状態を評価する試験です。潤滑油の性能評価によく用いられます。日本で開発された曽田式は3/4インチ、欧米で主流のシェル式は12.7mm(1/2インチ)の試験剛球を用います。
ピンブロック試験
円筒の試験片をV溝の入ったブロックではさみ、試験片を回転させて摩耗状態を評価する試験方法です。特に、潤滑状態での焼付き評価に適しています。
自動車部品の摩耗試験結果を実務に活かすポイント
自動車の摩耗試験は、単に数値を測定するだけでなく、実際の開発や保守に活かすことが重要です。トライボロジーの視点から摩耗特性を理解することで、部品の寿命や性能を高める具体的な対策につなげられます。
活用のポイントは、以下のとおりです。
- 試験データを設計段階で反映し、材料や表面処理を最適化する
- 摩耗の進行傾向をもとに保守・点検スケジュールを見直す
- 潤滑油の選定や添加剤配合の改善に活かす
- 量産段階ではロット間のばらつき管理や品質チェックに活用する
これらの対応を行うことで、摩耗による故障や異常を未然に防ぎ、安全性や燃費、耐久性といった自動車性能の安定化に直結します。摩耗試験は、トライボロジーの知見を開発現場や生産現場に橋渡しするために重要です。
摩耗データを活かした自動車エンジンのメンテナンス活用
摩耗試験で得られたデータは、自動車のエンジンや駆動部品の性能評価だけでなく、日常のメンテナンス計画にも役立ちます。トライボロジーの観点から摩耗傾向を把握することで、部品の交換時期や潤滑油の見直しなど、具体的な対策に結び付けられます。
摩耗データ活用のポイントは、以下のとおりです。
- 摩耗進行の予測:試験結果から摩耗速度や部品寿命を推定し、交換タイミングを計画
- 潤滑油の最適化:摩耗データに基づき、エンジン内部で最適な潤滑条件を選定
- 点検優先度の決定:摩耗が進みやすい部品を特定し、日常点検や整備スケジュールに反映
- 異常検知の参考:試験値と現場データを比較することで、異常摩耗の兆候を早期に発見
このように、摩耗試験のデータを活用することで、エンジンやトランスミッションの寿命を延ばし、安全性や燃費、耐久性の向上に直結します。トライボロジーの知見を現場で活かすことで、未然に故障を防ぐメンテナンス戦略が可能になります。
トライボロジーのエキスパートをお探しならTAS研究所へ
TAS研究所は、トヨタ自動車・アイシンで、トライボロジー(摩擦・摩耗・潤滑)のエキスパートとして材料研究・開発および設計支援に従事してきた経験を活かし、摩擦・摩耗・潤滑といった接触メカニズム解析から原因推定と接触界面の最適化(潤滑剤、材料、設計)をご提案いたします。また、必要に応じて機械試験をパートナー会社に依頼し、結果を解析して報告いたします。試験が特殊かつ恒久的に必要な場合、設備を設計製造して納入することも可能です。
詳細が知りたいという方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
【トライボロジー】機械故障・解析や摩擦試験に関するコラム
- 機械故障について専門家に相談を!漏油・過熱トラブルの原因と対策
- 急ぎ対応が求められる機械故障時の注意点と早期対応のポイント
- 【機械故障】再発防止ならコンサルへ相談!メリット・選び方・具体的な進め方
- 機械故障コンサルティング完全ガイド!専門家の役割・選ぶ基準・費用について
- 【トライボロジー】自動車の摩耗の基本や試験について
- トライボロジーで探るかじりの原因と潤滑技術による防止策
- 摩擦試験の委託費用は?受託している業者の選び方や準備のポイント
- 摩擦試験における係数測定・分析の重要性と腐食がもたらす影響
- 【機械の故障解析】原因究明の手法・手順・専門家に依頼するメリットを解説
- 【機械の故障解析】焼付きの対策と疲労破壊の現象解析手法
トライボロジー・摩耗対策のご相談ならTAS研究所
| 会社名 | TAS研究所 |
|---|---|
| 電話 | 090 8324 6136 |
| suzuki@taslab.jp | |
| 受付時間 | 9:00-18:00[ 土・日・祝日除く ] |
| URL | https://taslab.jp |